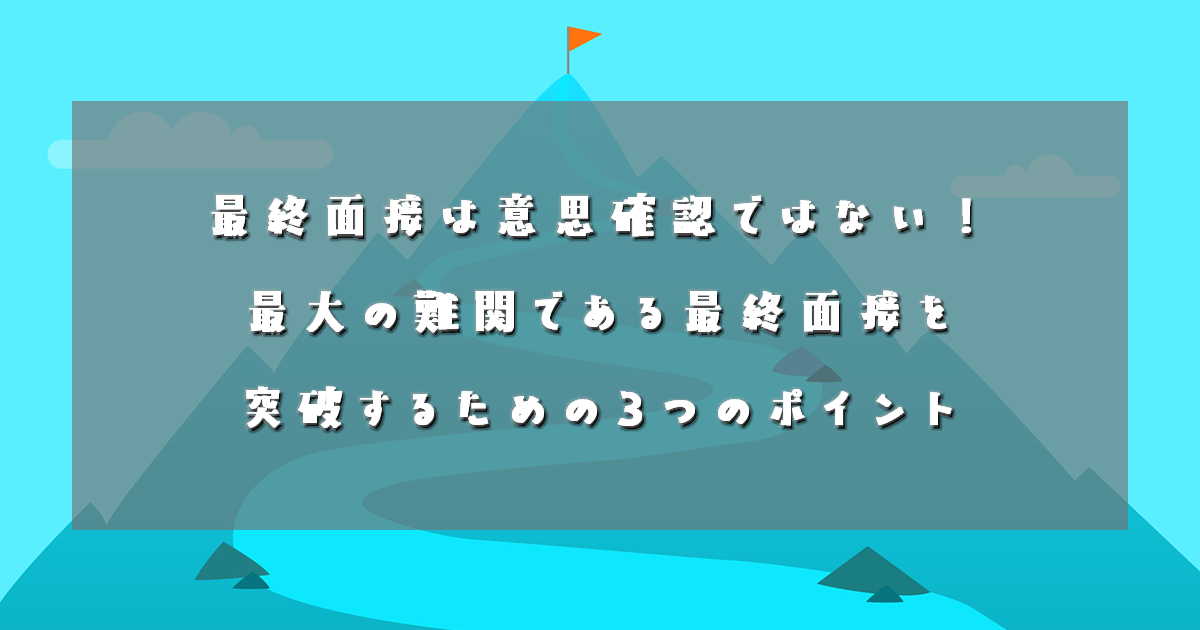転職活動をしていて、一次面接に合格して一喜一憂する暇はありません。
一次面接を突破したからと安心するのは時期尚早です。本当の勝負はこれからです。
「最終面接は『意思確認の場』ですよね?」
いいえ、それは大ウソ!当てはまりません。
一次面接でどれほど高い評価を受けていたとしても、最終面接での評価を下げれば、選考結果は不合格です。最終の次はもう無いので、挽回できず、自分自身の可能性が閉ざされてしまいます。
だからこそ、最終面接こそ、徹底的な準備をしてから面接に臨みましょう!一次面接に合格して、受かった気になるのは早いですよ。
この記事では、転職活動における最大の難関である最終面接で成功するための3つのポイントを解説します。
そのポイントとは、以下の3つです。
- スキルや経験は一次で評価されている
- ミスマッチを見破れるな
- 基本に立ち返って復習する
それでは、順番に解説していきます。
目次
ポイント①:スキルや経験は一次で評価されている
最終面接に進めたということは、一次面接でスキルや経験については「問題なし」と評価を受けたことになります。
自分がやってきたことは間違っていなかったということですし、スキルや経験を認めてくれたことは素直に喜んでいいことですし、自信を持っていいと思います。
一次面接と最終面接の違い
一次面接と最終面接の面接官は同じではありません。
一次面接は、配属予定先の担当部署の責任者クラス(部長や課長など)、最終面接は人事権を持った役員クラス(本部長など)がそれぞれ担当しますので、面接で見られるポイントや評価されるポイントも違います。
最終面接では、スキルや経験があるのは当たり前、という状態からスタートし、あとは入社後に活躍してくれそうか、同僚など社内外の利害関係者とうまくコミュニケーションを図れそうか、職場の雰囲気や社風に合っているか、将来ビジョンやキャリアの方向性が会社が示す方針と合致しているかなど、既に一次面接で評価されているスキルや経験より深く見られます。
大事なことは一貫性
最終面接でもっと評価を得たいからと、過度な意気込みや背伸びをするのは逆効果です。
きっと最終面接は、一次面接よりも緊張するかもしれませんが、一次面接と同じ内容でも構わないので、面接の質問には一貫して答えることが重要です。
選考で伝えるべきは、自分を採用することで企業にもたらされる価値やメリットです。一貫性を持って自分自身をアピールすることで印象は良くなります。
ポイント②:ミスマッチを見破られるな
最終面接は、面接官も真剣です。
どんなに能力が高くて、優秀でも、応募した求人内容に対して少しでもミスマッチを感じさせてしまえばお見送り確実です。
最終面接というのは実力だけでなく、企業や求人へのフィット性であったり、志望度の高さも重視されます。何故なら、入社してすぐに辞められては困るわけで、これから末永く会社に貢献できる人材であるかを確認しています。
中途半端な気持ちを見せない
最初から辞退する気で最終面接を受けに来ようと思う人なんてまずいませんし、面接官も最初から不合格を出すつもりで面接をすることはありません。
最終面接に進むということは、もし内定が出れば入社を決め働く意思があると期待します。
もちろん辞退することは可能ですが、もし本当にそうだったとしても、それは最終面接という場で相手に見せる必要はありません。
一度内定が出されれば、その瞬間に立場が逆転し、候補者は「選ばれる側」から「選ぶ側」になります。その段階で他の企業と比較して、内定を辞退することも可能です。
ミスマッチかどうかは面接官が決める
例えば、実は他の企業や職種に興味がある、別の仕事に未練がある、といった入社する覚悟が足りていなかったり、それを言葉にしなかったとしても、最終面接の場でその意向をうっかり見せてしまえば、不採用リスクが高くなってしまいます。
自分にはそのつもりはなくても、面接での言動や態度で相手の期待に応えられず、面接官に「ミスマッチ」と受け取られてしまえば、それは採否に大きな影響を与えることになります。
そのため、最終面接ではこうした誤解を招かないように十分な注意が必要です。
相手が期待していること、求められていることを理解し、迎合する、つまりそれを演じることも時には必要です。
ポイント③:基本に立ち返って復習する
どんな面接でも基本に立ち返ることが重要です。
過去に私は最終面接で苦い経験をしました。その時は一次面接の評価が高く、面接官からも最終面接で落ちないようにと応援されるほどでした。
だから、その状況に「もう受かったも同然」、「意思確認だけだろう」とろくに対策も行わず、最終面接に臨み、結果は不合格。
最後まで気を緩めず、緊張感を持って対策して欲しいです。
基本を押さえる
転職面接の基本が「転職理由」であることは一次面接も、最終面接でも変わりません。
最終面接に進めた段階でスキルや経験は既に一定の評価を得ているわけですから、最終面接への対策としては、再度基本に戻り、転職理由の客観性と論理性を確認することが重要だと思います。
話の筋は一次面接と大きく変えず、転職理由を伝える際のロジックや表現は適切かどうかをもう一度精査します。
一次面接では細部について追求を受けなかっただけかもしれないので、最終面接の面接官がそれに気付き、質問攻めにあうかもしれない、という思いで取り組みましょう。
志望動機と自己PRの整合性を確認
転職理由だけでなく、志望動機と自己PRも面接では必ずと言っていいほど聞かれます。
転職理由は、現職への不満の裏返しです。志望理由は、転職理由になった不満を解消できているか、この繋がりが必要です。自己PRは、志望理由を支持する根拠であり、転職後に自身がどのように価値を提供できるかを示す重要な要素です。
次が最終面接であっても、仮に一次面接で評価を受けていたとしても、面接前は基本に立ち返り、これらの整合性を確認することが重要です。
職務経歴書にも目を通し、これらの要素をしっかりと結びつけて考え、磨き上げることに時間を使って欲しいと思います。
私の失敗体験:最終面接での不合格体験
最終面接でのまさかの「不合格通知」。
面接前は、まさか自分が不合格になるとは夢にも思いませんでした。今回は、過去の最終面接での失敗体験を共有したいと思います。
皆さんは、私のようになってはいけません!
受ける前からの自信過剰
ある企業の最終面接に挑戦しました。その前の一次面接での印象がとても良く、高い評価を受けていました。面接官から「一緒に働きたいと思っています!」と言葉をかけて頂き、面接の合格通知は当日に届いたほどでした。
この状況から、私は合格を確信していました。自分を過信し、すでに内定を手にしたような錯覚に陥り、最終面接に向けた準備を軽視していました。新しい仕事でのキャリアビジョンを考えるのではなく、その会社周辺の物件を調べるのに時間を使っていました。
しかし、結果は思い通りにはならなかったのです。
失敗の原因と教訓
私は、エージェントのコンサルタントを通じて、無理を承知でその企業の面接官に不合格の理由を直接尋ねました。何故、自分が不合格とされたのか、当時はまだ理解できずにいたからです。
その回答によれば、『質問に対しての回答の明確さなどが、どうしても気になってしまい、そこで感じた不安を面接の中の他の部分で払拭することができなかった』とのことでした。最終面接への準備を怠り、面接官に入社後の自分の姿について8不安を抱かせてしまった可能性があります。
この経験から得た教訓は、最終面接においては軽率な態度ではなく、しっかりとした対策が必要であるということです。他の人が私と同じ道を辿ることのないように、私は声を大にして言い続けたいです。
最後は熱意
仕事に熱意を持って取り組める人とそうではない人がいたら、どちらを採用したいですか。
どんな面接でも「貴社が第一志望である」と熱意をはっきり示すことが重要です。
最終面接に進んでいる候補者は自分一人とは限りません。他の候補者と比較し、面接での人物評価が同じなのであれば、企業は志望度の高い候補者を選ぶと思いましょう。
それくらい最終面接では「確実に入社する意志」を面接官に伝えることが大切です。
最後に
いかがでしたか。
最終面接の対策について解説しました。
私の後輩は、最終面接の場が転職理由の深掘りに費やされ、質問攻めにあったようです。
一貫性や合理性が無いと判断されてしまうと、面接官は次々と納得するまで質問を続けます。結局、面接時間いっぱいが転職理由の確認の終わり、後輩は不合格となってしまいました。
最終面接だからこそ、一度基本に立ち返り、しっかりとした対策を講じて臨んでいただければと思います。